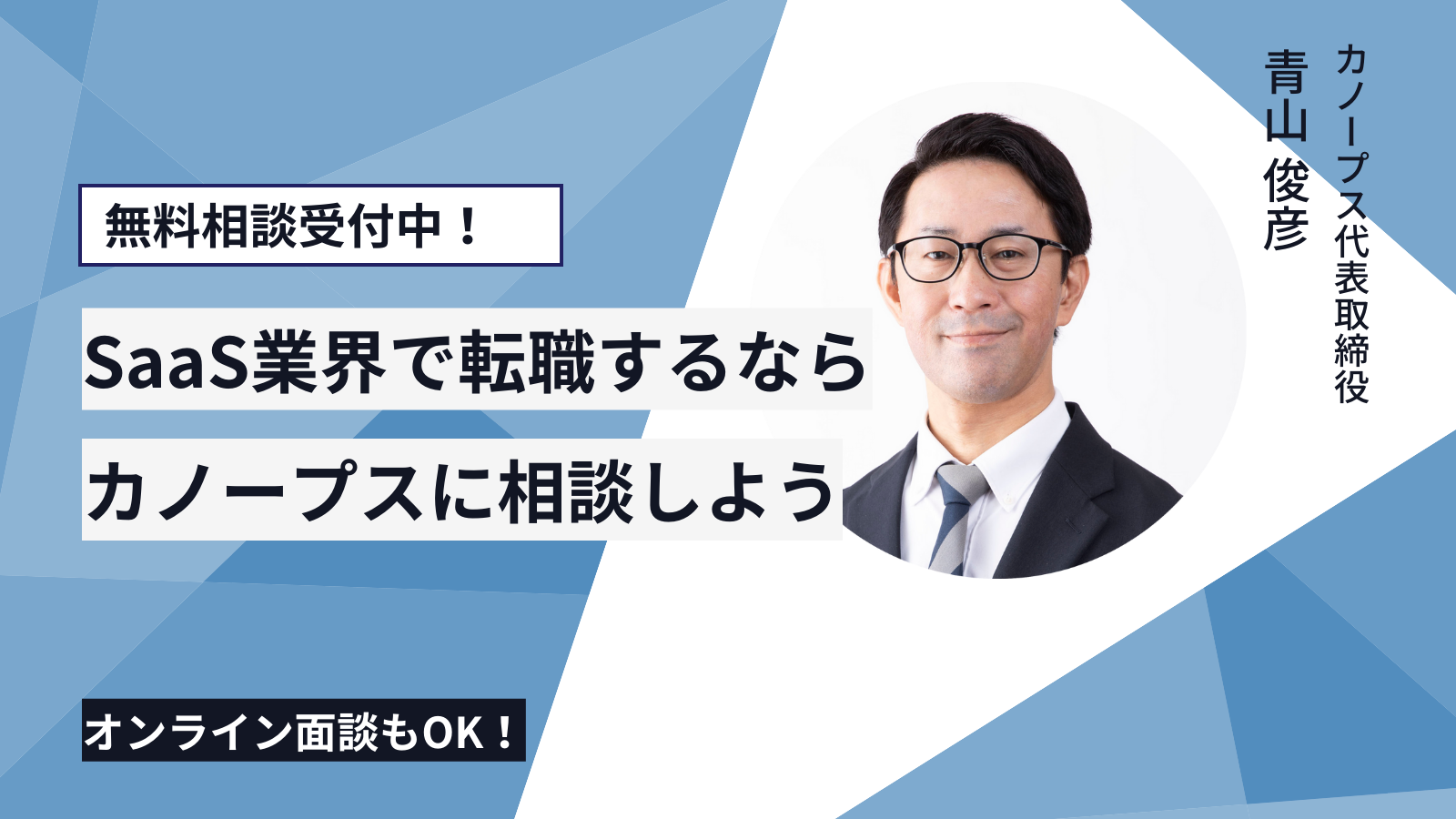近年、SaaSをはじめとした多彩なITサービスの普及とリモートワークの浸透により、企業内での「シャドーIT」問題が懸念されているようです。例えば、SlackやNotion、Figmaなどの便利なSaaSツール、情報システム部門の承認なしで導入していませんか?本記事では、シャドーITの定義と背景、放置することによるリスク、そして企業が取るべき対策について、実践的な視点から詳しく解説します。
シャドーITとは何か?その定義と現状
「シャドーIT」とは、企業の情報システム部門が把握・管理していない状態で、社員や部署が独自に導入・使用しているITリソースを指します。かつては私物のノートPCやUSBメモリなどが中心でしたが、現在では主にSaaSツールの無断利用も問題視されるケースが増えているようです。
たとえば、ある営業部門がチーム内のコミュニケーション効率を高めるために、会社に無断でSlackの無料プランを導入する。あるいは、デザイン部門がプロトタイプ作成のためにFigmaを勝手に使い始める。こういった行為が、まさにシャドーITの典型です。
こうした行為の根底には、「使いやすさ」「即効性」「現場主導での改善」という前向きな動機があります。しかし、それが組織全体でのセキュリティガバナンスやライセンス管理と乖離したとき、大きな問題を引き起こす可能性があります。
なぜSaaSライセンスがシャドーIT化するのか
SaaSツールのシャドーIT化が進む背景には、いくつかの構造的要因があります。
・導入の手軽さ
多くのSaaSは無料プランやトライアル期間があり、クレジットカードさえあれば個人でも即日で利用開始できます。情シスの承認プロセスを待つより、自分たちで試してみた方が早いという現場の意識が根底にあります。
・業務のスピード重視の文化
特にスタートアップやSaaS企業では、「すぐ試す」「早く動く」が価値とされる風土があり、IT統制よりも現場の判断が優先されがちです。
・リモートワークの一般化
情報システム部門がすべての業務ツールをリアルタイムで監視・統制するのが難しくなっており、社員一人ひとりが自発的に最適なツールを選ぶ傾向が強まっています。
放置すると企業にどんな影響があるのか?

シャドーITを放置することで発生するリスクは多岐にわたります。
・セキュリティリスク
勝手に使われているSaaSツール上に顧客情報や機密データがアップロードされている場合、適切なアクセス管理がなされていないと、情報漏洩や不正アクセスのリスクが急増します。
・コストの無駄
同じSaaSツールを部署ごとにバラバラに契約していると、ライセンスの重複やコストの最適化が困難になります。未使用アカウント(ゾンビライセンス)の存在も、無駄な支出につながります。
・情シス部門の業務負担
問題が発覚した後、「誰が、どこで、どのSaaSを使っていたか」の棚卸しや監査が必要になり、緊急対応に追われることになります。
シャドーIT対策の最前線:SaaS管理ツールとは
こうしたリスクに対抗するため、近年注目を集めているのがSaaS管理ツール(SaaS Management Platform)です。「Zylo」「BetterCloud」「Torii」などのプラットフォームは、社内で使われているすべてのSaaSを可視化し、使用状況の分析、ライセンス管理、アクセス制御などを一括で行うことができます。
これらのツールを導入することで、情シスはリアルタイムでSaaSの利用状況を監視でき、未承認ツールの早期発見や、使用頻度の低いアカウントの整理が可能になります。また、アラート機能や自動レポートによって、セキュリティインシデントの早期対応も期待できます。
企業規模が大きくなるほど、こうしたプラットフォームの必要性は増しており、今後は多くの企業で標準化が進むと考えられています。
情シスと現場が協力するための実践的アプローチ
シャドーIT対策の最も本質的な部分は、「文化づくり」にあります。つまり、情シス部門と現場の信頼関係を築き、「まず相談してもらえる」環境をつくることが重要です。
・情シスは監視者ではなく、業務改善のパートナーとしての立場を取る
・SaaS利用に関する社内ガイドラインを整備し、その必要性を丁寧に説明する
・「SaaS相談会」「業務効率化ツール紹介セミナー」などを通じて現場と対話する
こうした取り組みを重ねることで、現場の自発的な行動を抑制しながら、企業全体のITガバナンスを高めていくことが可能になります。
まとめ
SaaS時代において、シャドーITはもはや無視できない経営課題のひとつです。利便性とスピードを重視する一方で、セキュリティとコストの観点からも適切な管理が必要です。SaaS管理ツールの導入や情シスと現場の連携強化を通じて、企業全体でのITガバナンスを確立していくことが、今後の持続的成長の鍵となります。