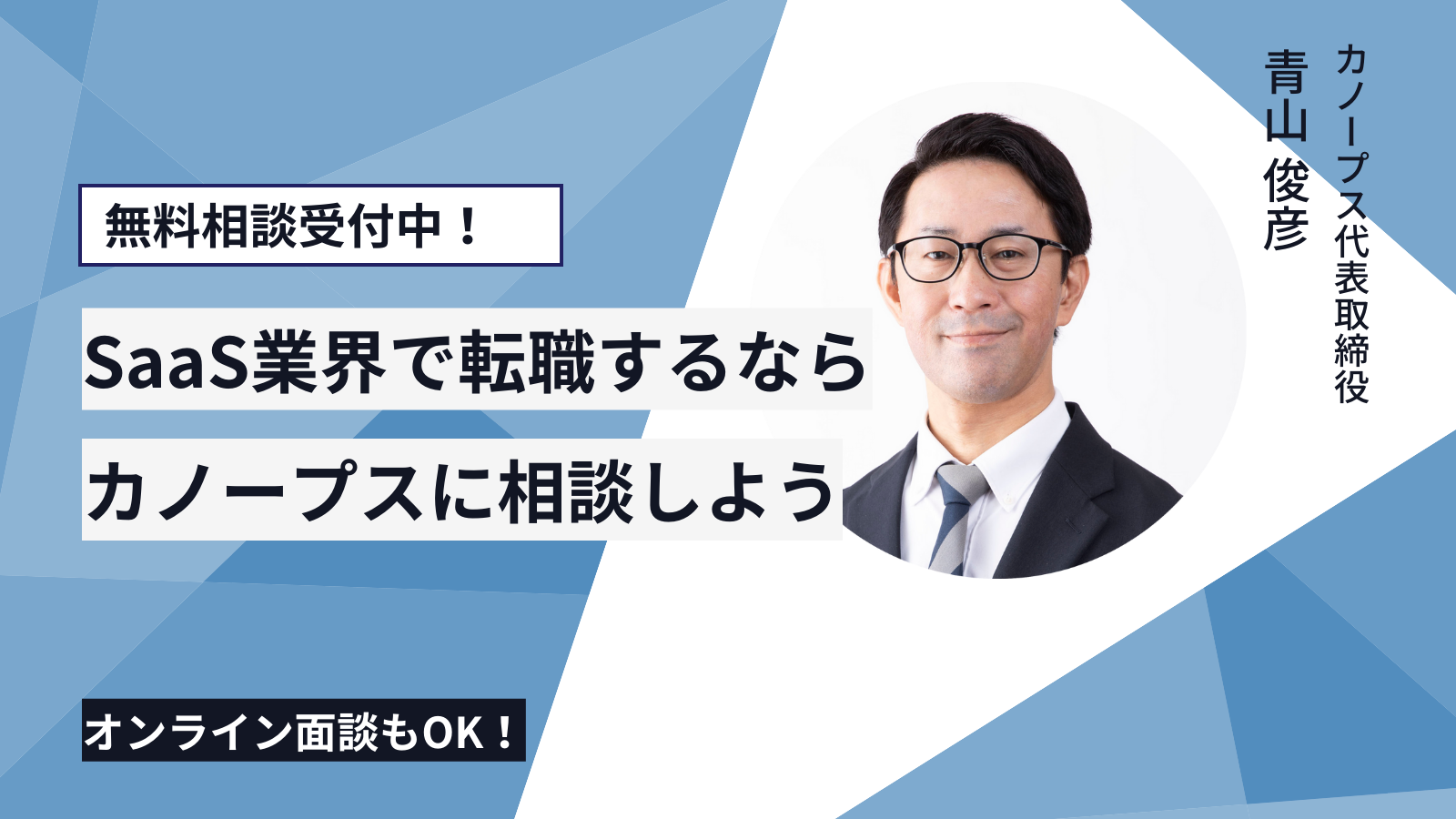近年は最新のテクノロジーをいち早く取り入れ、業務の効率化やスピードアップを実現することが日常となっています。しかしその裏で見逃されがちなのが、技術の進化とともに生じる「テクノストレス」です。テクノストレスは働く人の心理的負担を増やし、やがて組織への帰属意識やモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。本記事では、最新の研究を踏まえて、テクノストレスの実態、対処法、そして転職時に注目すべき点について詳しく解説します。
テクノストレスとは何か:定義とSaaS業界での現状
テクノストレスとは、情報技術の過剰な使用や急速な変化によって生じるストレスを指します。この概念自体は1980年代から知られてきましたが、近年はSaaS、クラウド、AI、自動化ツール等が急速に普及したことで、その影響範囲がさらに広がっています。
特に成長中の業界では、業務の中心に複数のツールが存在し、Slack、Notion、HubSpot、Salesforce、Asana、Zoomなどがフル稼働している環境が一般的です。そうした環境では、
・新しいツールが頻繁に導入されることへの不安
・「使いこなせていない」と感じる自己効力感の低下
・常時通知や即レス文化による疲弊感
・複数のシステム間を行き来することによる集中力の分断
といった現象が見受けられます。
この傾向は、特に非エンジニア職、管理部門、営業職など、ITツールの専門外の業務を担当する人に顕著です。技術は本来、業務を効率化する手段であるはずですが、それが目的化すると、逆にストレスの温床となりがちです。
テクノストレスが組織コミットメントに及ぼす影響
2023年に発表された研究「Examining the Impact of Technostress on Perceived Organizational Commitment: The Mediating Role of Individual Innovation」では、テクノストレスが従業員の知覚された組織コミットメントに与える負の影響、および個人イノベーションがその間を媒介することが確認されています。
この研究の主な知見は以下のとおりです。
・テクノストレスは組織コミットメントと個人イノベーションの両方に対して有意な負の影響を持つ。
・個人イノベーションは組織コミットメントに対して正の影響を持つ。
・個人イノベーションはテクノストレス→組織コミットメントの間で部分的に媒介 (mediator) として機能し、テクノストレスの悪影響を軽減する役割がある。
例えば、以下のような例。
・業務フローがツール主導で決まるため、個人の裁量や創意工夫の余地が減る
・頻繁なツール変更やアップデートにより、継続的に学び続けなければならないプレッシャーがある
・「できて当たり前」という期待が暗黙に存在し、サポート体制が十分でないことから孤独感を覚える
こうした要因が重なると、従業員は「疲弊感」や「無力感」を抱きやすくなり、結果的に組織コミットメントやエンゲージメントの低下、離職率の上昇につながることがあります。
個人イノベーションがもたらす緩和作用
前述の研究が示すように、テクノストレスと組織コミットメントの関係において、個人イノベーションは重要な緩和要因となります。すなわち、ストレス下にあっても創造性や改善意欲を発揮できる人は、組織への帰属意識を維持しやすいということです。
個人イノベーションには具体的には次のような行動が含まれます。
・日々の業務に対して新たな工夫を加えること
・既存のやり方を見直し、より効率的なプロセスを提案すること
・新しいツールを試し、その活用方法や知見を社内に共有すること
・社内外のベストプラクティスを取り入れて、チームに貢献すること
こうした行動が促進される環境では、従業員は自分自身の存在価値を感じ、仕事への満足度や意欲が高まります。一方、改善提案が無視される、挑戦が歓迎されないような環境では、個人イノベーションは抑制され、テクノストレスは増幅します。
具体的対策:企業と個人双方の視点から

テクノストレスを軽減し、組織コミットメントを高めるためには、企業側と個人側それぞれのアプローチが必要です。
企業側の取り組み
・ツール導入時には背景と目的を丁寧に説明したうえで、段階的に浸透させる
・操作方法や活用事例をまとめたマニュアルやオンボーディング研修を用意する
・心理的安全性を意識し、不安を受け止める組織文化を醸成する
・社内に「ツールアンバサダー」を配置し、ツールの使い方や効率的な運用を支えられる体制を整える
個人側の工夫
・使いこなせない部分をネガティブにとらえず、学びの機会と位置づける
・通知・チャット・タスクなどの情報の取捨選択を意識し、優先順位を明確にする
・業務改善アイデアを小さな単位から試してみる
・業務中に感じるストレスの要因を上司やチームで定期的に共有する
これらの取り組みによって、テクノストレスを完全に排除することは難しくても、その影響を最小限に抑え、自分自身の働き方に主体性を取り戻すことが可能になります。
転職を考える際に注目すべきポイント
テクノストレスの存在は「見えない転職リスク」といえます。転職を考えている方は、以下の観点を重視して企業や環境を見極めることをおすすめします。
・面接時に「社内で使われているツールの種類・数」や「ツール導入の背景・導入プロセス」について具体的に聞く
・入社後の研修やオンボーディング体制が整っているかどうか、学びのサポートがあるかを確認する
・失敗を恐れずに提案できる雰囲気があるか、社員の声が組織に反映される風土があるかどうかをチェックする
・在籍社員の口コミやレビューサイトなどで、「ツールによるストレス」がストレス要因として挙げられているかを調べる
また、自分自身のストレス耐性や変化への柔軟性について棚卸しをしておくとよいでしょう。現職に不満があっても、「何が具体的にストレスなのか」を把握できていれば、転職先とのミスマッチを防ぎやすくなります。
まとめ
本記事では、テクノストレスの定義、その組織コミットメントへの影響、個人イノベーションの緩和作用、具体的な対策、そして転職時チェックポイントまでを整理しました。重要なのは、テクノストレスを恐れるのではなく、変化を受け入れつつ、主体的に働き方をデザインしていく力をつけることです。企業としても、個人としても、柔軟性を備えた環境とマインドを育むことが、今後ますます価値を持つでしょう。転職を検討する際にも、「テクノストレス」の観点を判断軸の一つに加えてみてください。