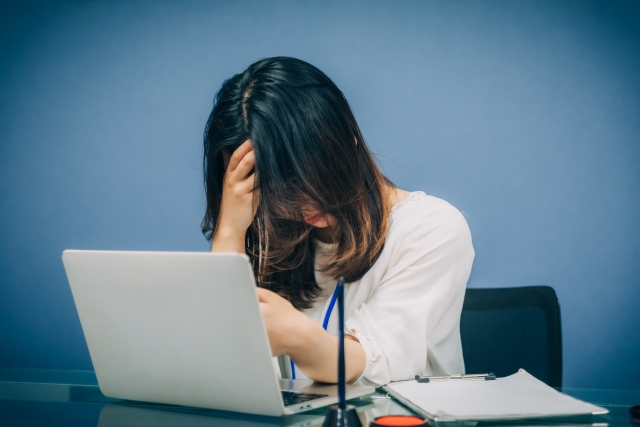企業が成長を遂げ、規模が拡大するにつれて、初期段階では表面化しなかった問題が姿を現しやすくなります。とくに「派閥」「セクショナリズム」「人間関係悪化」といった組織の負の側面は、従業員の離職やモチベーション低下、生産性の低下、さらには企業の社会的信頼の揺らぎにまでつながりかねません。本記事では、これらがなぜ発生し、どのように組織に影響を及ぼすのかを整理するとともに、具体的な対策を考えてみます。
組織の成長がもたらす人間関係の歪み
成長初期の企業や組織は、共通の目標に向かって協力しやすく、コミュニケーションも自然にはじめやすい環境があります。しかし、規模が拡大すると、部署やチームが細分化され、物理的にも心理的にも分断が生じやすくなります。その結果、以下のような歪みが徐々に浮上してきます。
・部署間の連携が希薄になり、他部署をライバル視し敵対関係が生まれる
・価値観や文化の違いが顕在化し、小さな不和が膨らみやすい
・共通の「顔」が見えにくく、企業全体への一体感が薄れる
・顔の見えない構造の中で、不当な扱いや情報の偏在が放置されやすくなる
こうした状態は、結果として組織の硬直化や非効率化を招く温床となります。
なぜ派閥が生まれるのか?その背景と対処法
派閥とは、意見や価値観の違いに起因して、職場内で自然発生的に生まれる集団です。人は共通点を求め、その中に安心感や支持を感じる傾向がありますが、これが偏った同調の構造を生み、対立を深めることがあります。
主な背景には以下があります。
・共通の価値観や趣味・バックグラウンドを持つ者同士の集団化
・情報格差や支援の集中による排他的構造の形成
・非公式な力関係の出現と、それへの同調圧力
・意見や価値観の合わない人や物事への「仲間外れ」や「無視」といった心理的抑圧の発生
派閥による弊害は、業務連携の停滞や情報交換の阻害だけでなく、対象とされる個人への精神的ストレスや組織全体のモラル低下、離職へつながるケースも少なくありません。
対処法としては次のような手段が有効です。
・ジョブローテーションや横断的なプロジェクトを通じて、メンバー間の分断を解消する
・共通のビジョンやミッションを社内で丁寧に共有し、組織全体の一体感を育む
・オープンで双方向なコミュニケーションを促進する(1on1や全社ミーティングなど)
・公正な評価制度と透明性のある判断基準で、偏りのない職場文化をつくる
これらの手法を組み合わせることで、派閥化の芽を未然に摘み、組織全体の調和を確保できます。
セクショナリズムが引き起こす構造的弊害
セクショナリズムとは、部署やチーム単位で縄張り意識が過度に強まり、他部署との協力を拒む状態を指します。特に組織が大きくなると、セクショナリズムは頻繁に見られる課題です。
特徴的な問題点としては次のようなものがあります。
・他部署との非協力による情報のブラックボックス化
・責任のなすりつけ合いから派生する不信感と対立
・「自部署最優先」文化が生む短期思考と全体視点の喪失
・結果としてイノベーションの鈍化や意思決定の遅延
対策としては以下のようなものが効果的です。
・部署横断的なチームやプロジェクト編成で協働関係を強化
・評価制度を、部署の成果だけでなく、他部署への貢献意識も反映するように見直す
・社内SNSや交流イベントで物理的・心理的な壁を取り除く
・経営層のメッセージによって「全社視点」を明文化し、全従業員に浸透させる
これにより、部署単位で閉鎖化した文化や考え方を打破し、組織全体の連帯感と柔軟性を高めることが可能になります。
いじめ・ハラスメントの実態と組織への深刻な影響

職場で起こるいじめやハラスメントは、「パワーハラスメント」に象徴される通り、単なる個人間のトラブルではなく、組織文化そのものの問題へ発展します。
発生しやすい環境には以下が挙げられます。
・長時間労働や休日出勤が常態化するストレス環境
・部門間の交流が乏しい閉鎖的な職場
・強圧的なリーダーシップや評価基準の曖昧さ
・偏見やアンコンシャス・バイアスに起因する無意識の差別
深刻な影響としては以下が挙げられます。
・被害者の心身の健康被害、モチベーション低下
・周囲の社員の不安感と傍観傾向の助長
・心理的安全性の低下による本音で話せない文化の定着
・離職率の増加、企業全体の生産性・品質の低下
・ブランドイメージや社会的信頼の著しい損失
有効な対策には以下のようなものがあります。
・ハラスメント防止を明記した就業規則や指針の整備
・研修やワークショップで社員の理解を深める教育活動
・社員からの匿名相談窓口設置と早期対応体制の構築
・リーダー層への行動規範教育とモニタリング
・職場全体で心理的安全性を意識する文化づくり
これらを実行することで、いじめやハラスメントによる悪循環を断ち切り、安心して働ける環境を築くことができます。
組織を健全に保つために必要なアプローチ
企業や組織が健全な状態を維持し、さらなる成長を実現するためには、以下のような多角的アプローチが効果的です。
・組織文化の変革:企業理念やミッションを明文化・浸透させ、共通目標への意識統一を図る
・人事制度の見直し:ジョブローテーションや横断チームを活用し、固定化された派閥や縄張り意識を解消
・コミュニケーションの活性化:1on1ミーティング、メンター制度、ピアボーナス制度などを導入し、風通しの良い文化を醸成
・リーダーシップの質向上:変革型リーダーシップを重視し、リーダー自身が模範となって対話と透明性を示す
・継続的な評価・改善:施策の効果を定量・定性で定期的にレビューし、常に改善を続ける姿勢をもつ
これらは一つひとつが重要ですが、同時に連携させて全体戦略として進めることが、真の成果につながります。
まとめ
これまでご紹介してきた課題や対策は、規模や業種を問わずあらゆる組織にとって普遍的なテーマです。ただし近年では、SaaS企業のようなかつての成長段階にあった企業も、今や従業員数数百名、さらには数千名規模へと拡大しつつあります。その結果、これまで「スタートアップらしさ」の中で意識せずに済んでいた組織課題が、いまや現実のものとして直面され始めています。だからこそ、成長著しいSaaS企業においても、本記事で述べたような派閥・セクショナリズム・いじめへの洞察と予防策は、極めて有効かつタイムリーなものとなるでしょう。変化する組織環境に柔軟に対応し、健全な企業文化を築くことが、持続可能な成長を支える鍵となるはずです。
あわせて読みたい
変化に強い組織を作る「適応学習組織」の本質とは