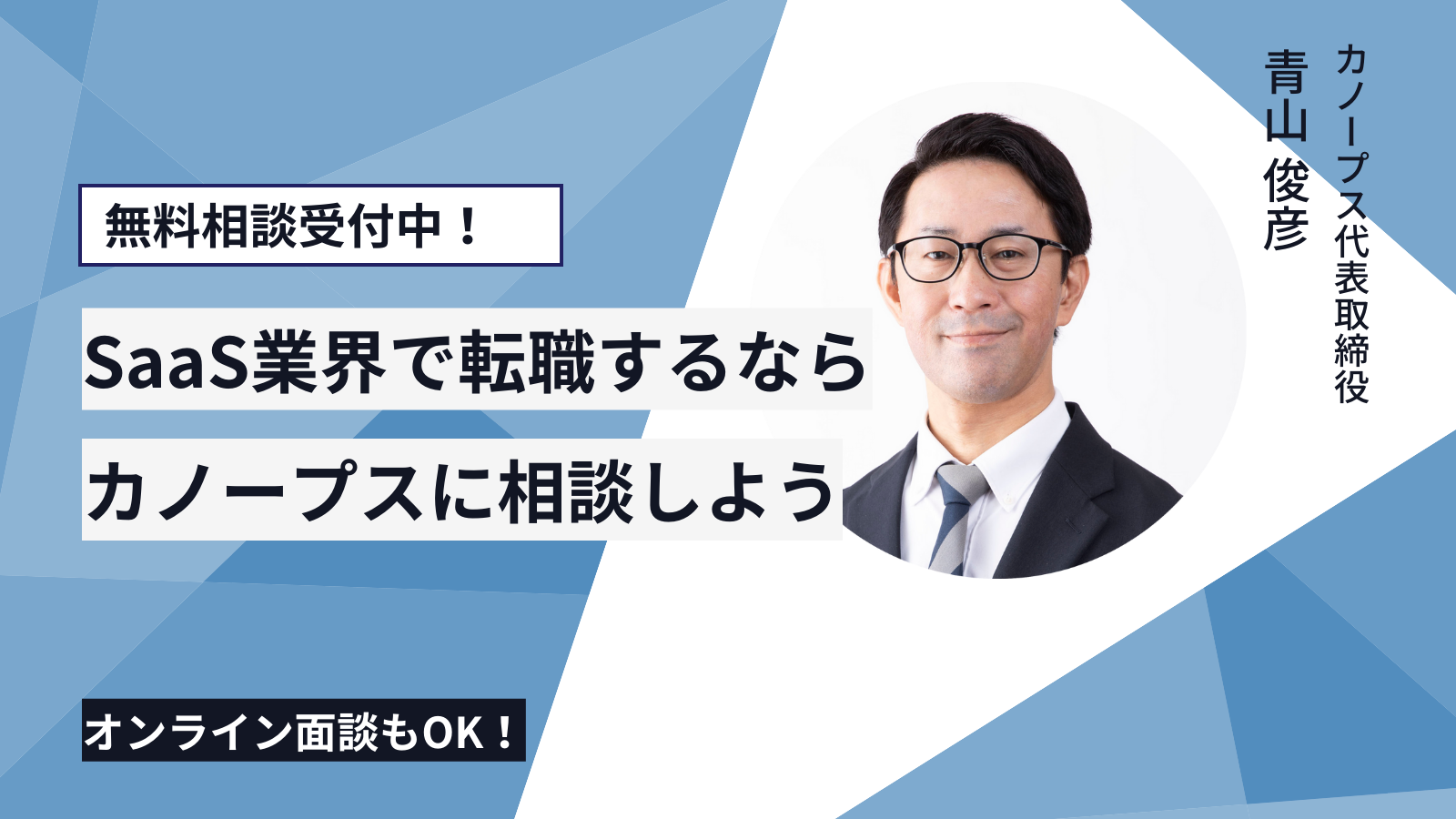大手IT商社からSaaSメガベンダーであるSmartHRへ。一見、順風満帆に見えるキャリアチェンジの裏側には、仕事に対する「もっと輝きたい」という強い意志と、市場の黎明期を切り拓く泥臭い挑戦がありました。
SaaS黎明期の関西マーケットを駆け抜け、パートナーアライアンス として圧倒的な実績を残してきた村上琢哉さん。現在は、マネージャーとしてチームを牽引し、SmartHRの次なる成長を担っています。今回は、彼のキャリアの転換点となった葛藤、そしてSaaSビジネスの最前線で掴んだ確かな手応えについて、深く掘り下げていきます。
盤石な大企業で感じた、見えないキャリアの壁
―― まずは、現在の村上さんの役割と仕事内容について、自己紹介を兼ねて教えていただけますか?
私は現在、SmartHR関西支社に所属し、パートナービジネス事業本部のパートナーアライアンスで部長を務めています。パートナーアライアンスでは、主に名阪北陸エリアを担当しています。
主な活動内容は、金融機関や販売代理店と協力し、その先にあるお客様にSmartHRをお届けするための戦略を練ることです。また、新しいパートナーを開拓したり、既存のパートナーを支援したりもしています。
―― 多くの業務を兼務されていると思いますが、仕事で一番時間を使っていることは何でしょうか?
間違いなく、一番時間を費やしているのは「人」と向き合うことです。
プレイヤーだった頃は、自分の数字をどれだけ達成できるかに注力すればよかったのですが、マネージャーとして責任を持つ今は、自分一人の力ではなく、チーム全体の力を最大限に引き出すことがミッションです。
メンバー一人ひとりの個性や強み、そして弱い部分を深く理解し、私がどこで役に立てるのかを見極める。こうした人と向き合う時間が、大変でありながらも、一番のやりがいになっています。
―― 村上さんのキャリアは、新卒で入社されたダイワボウ情報システム(以降DIS)から始まります。当時の仕事内容や、SmartHRへ転職を考えるに至った経緯をお聞かせください。
はい。まず新卒でDISに入社し、渋谷・世田谷エリアの営業を担当していました。
当時のDISは、多くのメーカーの商材を扱う、まさに日本のIT流通を支える大企業でした。全国の販売店と取引があり、そこからいただく依頼にどれだけ応えられるかという営業スタイルが主流。社内には、その盤石な基盤の上で成果を出し続けるベテラン社員が多く、若手である私が売上という絶対的な指標で彼らに勝つのは難しいと感じていました。
当時の私は、どうすれば自分の介在価値を見出せるのか、どうすれば社内で存在感を発揮できるのかを常に考えていました。
受け身の営業から脱却。自らの手で仕事をつくり出した若手時代

―― その中で、村上さんはどのようにして自身の道を切り開いたのでしょうか?
メーカーから商品を仕入れて代理店に卸すのが商社の役割なので、DISで自社サービスを開発することはほとんどありませんでしたが、当時DISで「iKAZUCHI(雷)」というサブスクリプションサービスが開発されたんです。私はそこにチャンスがあると考えました。
代理店の共通の課題は、顧客ごとに異なる契約形態や満了日の管理が煩雑になることでした。「代理店の契約管理という課題を解決するソリューション」である「iKAZUCHI(雷)」はまさにこの課題に刺さるサービスです。積極的に提案したのです。
自ら自社の製品を売り込むこの動きは、当時のDISでは珍しいものでした。しかし、この地道な活動が功を奏し、他社からの切り替えを含めて多くの成約を獲得することができました。その結果、支店内でトップクラスの売上を残し、自分の存在価値を示すことができたと思います。
―― 素晴らしい実績を残された一方で、なぜ転職を考えるようになったのでしょうか?
実績を残せたことは大きな自信になり、やりがいも感じました。
当時のDISは強固で安定した営業基盤があり、安心感のある環境でしたが、一方で私はそこで培った経験を糧に、より大きな挑戦や新しい環境での成長を求めたいと考えるようになったのです。
「人」との出会いがキャリアを拓く:SmartHRへの決断

―― そのギャップが、転職活動のきっかけになったのですね。当時どのような軸で転職先を探されたのですか?
入社4年目の時に転職活動を始めました。
仕事へのモチベーションのギャップに加え、結婚を機に働き方や住む場所を見直すタイミングが重なったからです。妻も私も大阪出身なので、子供が生まれるタイミングで地元に戻りたいという気持ちが強かったんです。
DISにも全国に支店があるので、大阪勤務の可能性がないわけではありませんでした。しかし、せっかくなら外で自分の市場価値を知っておきたいという思いがきっかけになりました。
また、実際の転職先選びには2つの軸がありました。一つは、自分の介在価値を最大限に発揮できる「挑戦できる環境」。そしてもう一つは、「誰と一緒に働くか」という価値観です。
様々な企業を見る中で、これからパートナービジネスの組織や仕組みを作っていくSmartHRの環境と、「人」、そして「カルチャー」に強く惹かれました。
―― 具体的に、どのような点に惹かれたのですか?
面接で出会った人たちが、本当にいい人ばかりで。何よりも、フラットに話し合える文化に強く惹かれました。
入社年数に関係なく、ポジティブなこともネガティブなこともフラットに言い合える関係性は、自分にとても合っていました。入社4年目を迎えた今も、その魅力は変わらないと感じています。
ちなみに私は、学生時代にサッカーに打ち込んでいたのですが、その頃からフラットな関係性を大切にしていました。本当に勝つため、より良いものを目指すためには、上下関係なく意見を言い合える環境が不可欠だと感じていたからです。
―― 入社当時のSmartHRは、どのような状況でしたか?
当時のパートナービジネス事業本部は、まさに黎明期でした。
関西には私を含めて5人しかおらず、「まずは金融機関でやってみようか」というような手探りの状態でしたね。まだ組織としての形も決まっておらず、何もできていなかったからこそ、自分たちで作り上げていく楽しさがありました。
パートナービジネスの真価に気付いた瞬間

―― 黎明期は、壁も多かったと思います。どのような壁に直面しましたか?
はい。当時は社内外の両方に壁がありました。
まず、社内ではパートナービジネスが何をしているのか知られていませんでした。直販セールスからすると、「ややこしい」「調整が必要」といった理由で、パートナー案件は敬遠されがちだったんです。
社外では、そもそもSmartHRの認知度がまだ低く、パートナー企業にもなかなか相手にしてもらえない状況でした。
―― それらの壁を、どのようにクリアしていったのですか?
「成功体験を積むしかない」という思いで、泥臭く動き続けました。シンプルだけど根気は必要でしたね。
社内では、パートナーから良い案件を紹介いただけるよう働きかけ、温め育てて最高の状態で直販セールス繋ぐ。直販セールスが「これは良い案件だ」と思ってもらえるように徹底しました。一方、社外では、協力してくれるキーマンを見つけ、とにかく早く成功事例を作ることに力を注ぎました。
この地道な活動が実を結び、最初の1期目は順調に目標を達成できました。しかし、その結果2期目に見通しが甘くなり、成績が伸び悩んでしまったのです。
このままではいけないと深く考えた時、パートナービジネスの本当の価値は、ただ案件を渡すだけではないと気づきました。
―― それは、どのような気づきだったのでしょうか?
自分の介在価値は、直販部隊に良い案件をトスアップする「援護射撃」するだけではない。自社、パートナー、エンドユーザーの三方にとって良い結果になるよう、全体を指揮する役割なのだと気づいたんです。
サッカーで例えるなら、最前線でゴールを狙うフォワードでも、最後尾で守備をするセンターバックでもない。攻撃と守備をつなぎ、ゲーム全体をコントロールする「ボランチ」の役割です。
誰よりもパートナー、案件、自社の状況に対して解像度を高く持ち、社内外の連携を円滑にすることで、全体を動かしていく。それこそが、本来のパートナービジネスのあり方だと気づいてからは、物事の見方や行動をすべて変えました。そのおかげもあって、次の期では大きな目標達成につながりました。
「マネジメントするにはスキルが足りていない」から始まった、部長への道

―― 村上さんは2024年7月にチーフ、そして今年2025年1月にはマネージャーへと昇格されています。この異例のスピードでの昇格には、何か秘訣があったのでしょうか?
ありがとうございます。いくつか昇格の要因があったと思います。
当初は上司から正直に「お前は個人で数字は出せるが、マネジメントをするにはまだスキルが足りていない」と言われていました。私はプレイヤーとして、自ら前に出てどんどん仕事を進めるタイプで、自分でもその自覚はありました。しかし、それだけではいけないことも理解していました。そんなタイミングで、チーフに推してもらったんです。
チーフとしてマネジメントを経験するうちに、「一人の力には限界がある。メンバーの力を掛け合わせることで、1の力が10にも15にもなる」という面白さに気づきました。文字通り、どハマりしたと言ってもいいくらいです。
―― その「面白さ」が、マネージャーへのキャリアを後押ししたのですね。
そうですね。それから、パートナーアライアンスとしての現場経験に加え、前職の商社で培った視点も影響したのだと思います。
目の前の具体的な業務だけでなく、事業をどうスケールさせていくかといった、中長期的な視点で物事を考えられるようになっていたことも、評価していただけた要因の一つだと感じています。
―― 前職といえば、今は前職のDISにも関わっているそうですね。古巣と再び仕事をするのは、どのような気持ちですか?
はい。新規開拓にも力を入れていく方針となり、前職のDISとの協業に携わらせてもらっています。DISは地方に根ざした強固なディストリビューターであり、SmartHRと協力することで、より大きなスケールの取り組みができるのではないかという期待があります。
今の気持ちを一言で言うなら「楽しい」です。以前はがむしゃらに働いていましたが、いまSmartHRとしてDISと新しい可能性を模索していく中で、当時の上司や同期に連絡すると、皆協力的に耳を傾けてくれるんです。「面白そうだね」「もっとこうしたらどうだ?」と一緒にアイデアを出してくれることもあります。
会社は違っても、かつての仲間たちとまた別の形で仕事ができていることが嬉しく、過去の経験が今に活き、それが新しい価値を生み出していることを強く感じています。これは私自身のキャリアにとっても、SmartHRにとっても大きな意味があると考えています。
「Will」を尊重するマネジメント哲学
―― マネージャーとなった今、チームを率いる上で最も大切にしていることは何ですか?
まず、絶対にブレないようにしているのは、「理想とするパートナービジネス像」を伝えることです。パートナー、ユーザー、そしてSmartHRの三者がwin-win-winの関係を築くという「三方良し」の考え方が、このビジネスの根幹です。この軸は決してぶらしてはいけないと考えています。
その上で、メンバー一人ひとりを深く理解することに時間をかけています。目標という「高い山」」を登る方法は人それぞれです。自転車で登る人もいれば、遠回りをして景色を楽しむ人もいる。だから私は、「これが正解だ」と一つの道を押し付けるのではなく、メンバーの個性やモチベーションに合わせて、一緒に考え、目線を合わせることを大事にしています。
―― マネジメントを通して、村上さん自身が学んだことはありますか?
村上: マネジメントを通して、非常に多くのことを学ばせていただいています。
メンバーの多様な価値観や仕事への向き合い方から、「なるほど、そういう生き方もあるのか」と気づかされることも少なくありません。私の中での常識が覆されることも多々あり、マネージャーになってからの方が、むしろメンバーから学びを得る機会が増えたと感じています。
―― SmartHRで活躍している人には、何か共通点がありますか?
村上: 強いのは、やはり「素直さ」を持っている人ですね。
SmartHRのパートナービジネスは、まだ正解がないフェーズです。だからこそ、自分のやり方や思い込みにとらわれず、柔軟に意見を聞き入れ、「まずはやってみよう」と思える人が伸びます。
「どうすればもっと良くなるか」と常に自問自答し、周囲と意見交換しながら挑戦し続けられる人が、結果を出しています。
未来への挑戦:SaaS業界で描く、キャリアの多様性
―― 最後に、今後SmartHRで描きたい今後のキャリアや、SaaS業界を目指す方へのメッセージをお願いします。
村上:マネジメント経験については、引き続きもっともっと積んでいきたいと思っています。まだまだできていないことや、やれていないことばかりですからね。
その先を描くとしたら、「パートナーさんが自発的にSmartHRを売りに行ってくれるような仕組みやロールモデルを作ること」です。直販のような1対1ではなく、1対NでSmartHRがスケールできる世界を目指したい。SaaSでこれを成功させている会社はまだ少ないと思うので、日本ならでは、SaaSならでは、そしてSmartHRならではのパートナービジネスのあり方を証明したいです。
SaaS業界への転職を考えている方へメッセージを送らせていただくとしたら、「何を自分の中で一番のやりがいとするか」を明確にすることをおすすめします。
SaaSは新しい業界なので不安も多いと思いますが、自分がやりたいことを言語化できていれば、それに合った環境を探すことができます。そして、選んだ道を正解にするのは自分自身です。
SmartHRには、「Will(やりたいこと)」を持っている人がいいですね。自分の軸をぶらさず、素直さがあれば、きっと活躍できるはずです。

◼︎プロフィール
村上琢哉(むらかみ たくや)
2018年、ダイワボウ情報システムに新卒入社。パートナーセールスとして⻄東京営業部に所属し、新規代理店開拓やサブスプションサービスの展開に貢献。2022年、SmartHRに入社後は関西支社で黎明期だったパートナービジネスを推進。現在はパートナービジネス事業本部の部長を務め、名阪北陸エリアを管轄するアライアンスチームを率いている。